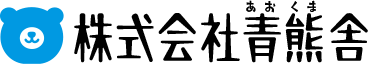【港区】セキュリティ教育動画|e-ラーニング活用のポイント
港区発!実務直結のセキュリティ教育動画|e-ラーニング最適化
近年、情報セキュリティの重要性が高まる中、港区の多くの会社でもセキュリティ教育の強化が求められています。しかし、「従業員に効果的な研修を行いたいが、どのような教材を選べばよいかわからない」「e-ラーニングを導入したいが、失敗したくない」、と言った悩みを抱える担当者の方も少なくありません。
こちらでは、セキュリティ教育動画の導入を検討している企業様に向けて、制作時のポイントやe-ラーニング活用のコツ、制作会社選びの注意点まで、実践的な情報をお届けします。効果的な社内研修の実現に向けて、ぜひお役立てください。
社内用セキュリティ教育動画|制作時に重要視すべきこと

社内向けのセキュリティ教育動画を制作する際は、効果的な学習と従業員の理解促進を目指すことが必要です。動画は、情報セキュリティの基本的な概念から最新の脅威への対策まで、幅広い内容を視覚的にわかりやすく伝える手段として非常に有効です。
教育目的の明確化とターゲット設定が第一歩
社内向けのセキュリティ教育動画を制作する際に、最初に行うべきは「目的の明確化」です。セキュリティ教育と一口に言っても、目的によって内容や構成は大きく変わります。例えば、「情報漏洩リスクの認識を高めること」が目的であれば、過去の事例をもとにリスクを実感できるストーリーが効果的です。一方で、「具体的な対処方法を覚えてもらうこと」が狙いであれば、手順を正確に伝える構成が求められます。
また、受講者の属性(新入社員、全社対象、技術職など)に応じて動画の難易度や用語の選定にも注意が必要です。全ての受講者に理解してもらうには、専門用語を避け、視覚的にわかりやすい演出が効果的とされます。
受講者の集中を保つ構成と長さの工夫
社内研修用の動画は、学習効果だけでなく「飽きさせない構成」も重要なポイントです。一般的に、人が集中できる時間は15分程度と言われているため、セキュリティ教育動画も1本あたり5~10分にまとめるのが理想です。長くなる場合は、テーマ別に分割して複数本のシリーズとして構成すると、受講者の理解度も上がりやすくなります。
また、図解を取り入れたりナレーション付きのスライド形式にしたりと、表現方法を工夫することで、受講者の集中力と記憶定着率を高められます。特にe-ラーニングで活用することを前提とする場合、クリックや小テストなどのインタラクティブ要素を組み込むと、学習への参加意識が高まります。
実務と直結する「リアリティ」が学習効果を左右する
研修教材としてのセキュリティ教育動画には、現場に即した内容であることも欠かせません。例えば、外出先での情報管理や、パスワードの取り扱い、怪しいメールの見分け方など、日々の業務の中で起こり得る具体例を扱うことで、受講者の当事者意識を高められます。
青熊舎が提供する動画は、ストーリー仕立てのため「自分ごと」として捉えやすくなっています。そうした教材は、学習効果を飛躍的に高める鍵になります。
セキュリティ教育動画|e-ラーニングを教材として採用する際のポイント

社内セキュリティ教育に動画を活用する際、e-ラーニング形式での提供は多くのメリットがあります。特に、多忙な社員でも自分のペースで学習できる点や、集合研修に比べてコストを抑えやすい点は大きな魅力です。
e-ラーニングに適した動画の形式と構成を設計する
セキュリティ教育動画をe-ラーニング教材として導入する際には、動画の構成と形式を適切に設計することが重要です。e-ラーニングでは、受講者が一人で視聴するケースが多いため、テンポが遅すぎたり、情報を詰め込みすぎていたりすると、学習意欲を損ねてしまうことがあります。
例えば、「パスワード管理編」「メールの取り扱い編」「端末の持ち出し編」と言った具合にテーマを分け、短くても要点がしっかり伝わる内容にすることで、集中力を維持したまま受講できます。こうした分割型の教材は、社内研修として繰り返し使う際にも管理がしやすく、LMS(学習管理システム)への導入もスムーズになります。
セキュリティ意識の定着には「反復」と「実践」の要素が不可欠
e-ラーニングの利点は、自分のペースで何度も繰り返し視聴できることにあります。これを活かすためには、受講者が「見て終わり」にならないように設計することが大切です。例えば動画の最後にミニテストや確認問題を挿入することで、理解度のチェックと復習ができ、記憶の定着にもつながります。実際の業務シーンを再現したシナリオと、インタラクティブな教材構成により、セキュリティ意識を行動レベルで身につけさせる効果が期待されます。
受講者に伝わる表現であるかも見極めるべき視点
どれだけ内容が正しくても、それが受講者に伝わらなければ教材としては不十分です。セキュリティ教育動画は、ともすれば堅苦しくなりがちなテーマですが、e-ラーニングの場では「見やすさ」「わかりやすさ」が最優先されます。
難解な説明やルールを羅列するよりも、日常業務での「ヒヤリハット」事例をもとにしたストーリー形式や、「社内あるある」を盛り込んだ構成にすることで、より身近に感じてもらえる映像になります。視覚情報を補足するテロップやアイコン、図解なども積極的に活用し、見た瞬間に理解できるような教材を目指しましょう。
【港区】セキュリティ教育動画|開発を依頼する際の注意点
制作会社との最初の打合せ時には、「研修の背景」「想定受講者」「社内での活用方法(e-ラーニングや集合研修など)」を明確に伝えることが、スムーズな動画開発につながる第一歩です。こちらでは、依頼時の注意点を解説します。
修正範囲・納品形式・使用条件を事前に確認する
セキュリティ教育動画の開発では、完成後に「思っていたものと違う」となるケースも少なくありません。その多くが、発注時に修正回数や納品形式についての取り決めが不十分だったことに起因します。
さらに注意したいのが利用範囲です。社内e-ラーニングでの使用は可能でも、外部向けにWeb公開する場合にはライセンスや著作権の問題が発生することが一般的です。動画の使用目的が多岐にわたる場合は、契約段階で利用範囲をしっかり確認しておきましょう。
制作会社の実績を確認する
依頼時には、「セキュリティ分野での制作実績があるか」「過去の教育動画でどのような工夫をしているか」と言う点を確認すると、その会社の強みが見えてきます。実績がある会社であれば、要望に対して「こうした方が効果的では」と言った具体的な改善提案を出せるため、信頼性の高いパートナーとなれます。
セキュリティ内容の正確性・最新性も重視する
セキュリティ教育は、正確な情報があってこそ成り立つものです。例えば、数年前の情報をもとにした教材では、すでに通用しない対策や古い事例が含まれている可能性があり、かえって誤解を招く恐れもあります。そのため、制作会社がどのような監修体制で動画を作成しているか、社内に専門知識を持つスタッフがいるか、または外部のセキュリティ専門家と連携しているかなど、信頼性の担保にも目を向けることが大切です。
【港区】セキュリティ教育動画やe-ラーニング教材の導入を検討中の皆様へ
青熊舎は、難解な情報セキュリティの知識を、アニメーションやストーリー仕立てで直感的に理解できる教育動画に変換します。リアルな事例や最新の脅威も、受講者が自分ごととして考えられるように設計いたします。
青熊舎の「WARABU」シリーズでは、落語アニメでランサムウェアなどのセキュリティリスクを楽しく学べるコンテンツを月額利用で提供しています。また、WARABUのキャラクターを使い、お客様の実際のインシデントや課題をアニメ化する、セミオーダー型サービスも対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。青熊舎が、お客様のe-ラーニング活用とセキュリティ教育の最適化を全力でサポートいたします。
Column
【港区】研修動画制作・e-ラーニング動画制作やセキュリティ教育動画に関するコラム
- 【港区】研修動画制作会社の選び方と依頼時のチェックポイント
- 【港区】研修動画制作の価格相場は?見積もり時のポイントも解説
- 【港区】セキュリティ教育動画|e-ラーニング活用のポイント
- 【港区】セキュリティ教育動画で社員教育|社員の意識を高めるポイント
- 【港区】アニメーション動画制作を依頼するなら|おすすめ会社と依頼の要点
- 【港区】アニメーション動画制作の費用は?相場を依頼先別に解説
- 【港区】企業向けe-ラーニング動画制作|効果的なコンテンツとは
- 【港区】e-ラーニング動画制作|教材の種類や外注のメリット・デメリット
- 【港区】新商品の販促|動画制作会社に頼む前に知っておくべきポイント
- 【港区】動画制作依頼から完了まで|サービスの流れと打合せのポイント
【港区】e-ラーニングやセキュリティ教育動画に関するご相談は青熊舎
| 会社名 | 株式会社 青熊舎 Aokumasha Co., Ltd. |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋3-1-2 笹井ビル5F |
| TEL | 03-6435-6881 |
| Eメールアドレス | info@aokumasha.com |
| URL | https://www.aokumasha.com |
| 提供サービス |
|
| アクセス |
|